2011年01月15日
1500年代府内の港には南蛮船
ポルトガル船は何故日本を目指したのでしょう
最初は琉球王国との交易を望みましたが、
琉球王国は、ポルトガルが、マラッカを占有したのを
警戒し断わりました。

マラッカ王国
1511年ポルトガルはインド総督アマフォンソ・デ・アルブケルケは、
18隻の艦隊と800名のポルトガル人を率いてマラッカ征服
日本の金や銀が目的だったみたいです。
何しろ、黄金の国 ジパング ですものね。
日本の黄金伝説は、奥州平泉の金色堂が十三湊経由で
中国に伝わり、マルコポーロへと伝わっていったようですね。
1500年代は、本当に大航海時代だったのですね。
しかし、この時代は、征服という行為が当然のごとく
行われていて、悲しい歴史も世界中で起こっております。
府内にポルトガル船が着始めたのが1500年代中頃からで、
ちょうどこの頃です。
2012年のJR大分駅前の高架完成に合わせ、
南蛮の風が吹いてくる。
>
戦国大名の大友宗麟がおさめた中世の府内を
イメージし広場内の照明にはステンドグラスを使用し
>
雨や日差しを除く歩道の屋根は、チタンを塗った幕を
使用し、帆船のイメージしたデザインを整備の予定

15世紀中頃のポルトガル船
きっと、心地よい南蛮の風が吹くでしょう。
1月17日より、大分市の大道陸橋が全面通行止めとなり
8月11日に新しい姿が見れるでしょう。

長い間本当に御苦労さまでした。
また、新しくなって違う姿を見せてください。
大道陸橋北の歴史を書かせていただきます。
江戸時代において、大道峠への街道が分岐する
三叉路となっていた。
明治時代、外堀は、西新町通りと南新町通りとなり、
大分市、南西端の交通の要であった。
1945年 焼け野原となる。
1946年に工事が始まり、昭和30年代に終わる。
旧三叉路より200メートル離れた大道陸橋北交差点が
市街地中心へと移る。

大道陸橋北交差点1月14日撮影
国道57号線起点 国道442号線起点 国道217号線終点
国道210号線終点 国道197号線終点 国道10号線
と交差しており、大分市の要」となっている。
大分の人はシャイなのか?
それとも、用心深いのか!
外国人の方ともっと気楽に話しましょう。
大分は医療最先端の県です。
昨年、メディカルバレー構想なる会が立ち上がりました。
http://www.san-gaku-renkei.com/news_a95AQqK4Q.html
大分から宮崎にかけての構想です。
大分には、人工腎臓で最大手の会社があります。
佐伯と三重には血液回路と生理食塩水を作っている
会社があります。
1500年代には、大分には府内病院がありました。
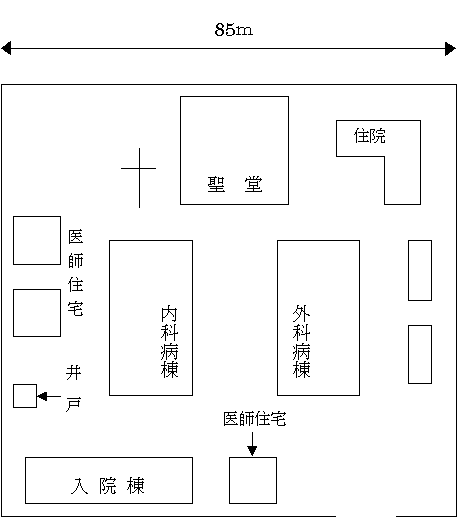 府内病院
府内病院
有名な医師ルイス・アルメイダが1557年私財をなげうって、
内科、外科、ハンセン氏病科の病院と当時、間引きを救うため
乳児院を開いた。
 ルイス・アルメイダの像
ルイス・アルメイダの像
すごいことです、この時代に外科手術も行っていたなんて。
現代でも、外国の方は、保険が使えず悩んでいる方や
どの病院にいけばよいのか、急病の時はどうすればいいかなど
悩んでいます。
外科と言えば近世になりますが解体新書で有名な中津の前野良沢がいます。
1771年杉田玄白とともに解体新書を書きましたが、
自分の名前は出さなかったみたいです。
 解体新書
解体新書
昨年、中世大友府内町跡よりワイングラスでは
ないかという、ガラスの破片が見つかっている。
(大友氏遺跡発掘現場より出土)
南蛮貿易でもたらされた品物が、その当時使用されていたなんて!
府内の街に南蛮文化が花開いていた。
そのころから、カンボジア、ヨーロッパとの交易があった証拠でもある。
その頃の府内の人たちが、日本で一番国際的であったのかもしれない。

南蛮屏風
大分は外国の方を受け入れる土壌が1500年代から
出来上がっていました。
鉄砲が種子島に伝来したのが1542年ですが、
なんと、2年後の1544年にはポルトガル人より、
大友家に鉄砲が献上されていました。

最初に種子島恵時親子が2丁の鉄砲を
今の相場で1丁 5千万円で買ったそうです。
それが、1575年の長篠の戦いでは3千丁、
1600年の関ヶ原の戦いでは5万丁、
当時日本の有する鉄砲の数は世界の半数を所有していたそうです。
鉄砲と言えば、堺が有名です、大友でも作れたはずなのに
なぜ、造らなかったのか、
やはり、貿易に頼りすぎたのか?
鉄砲保有量も、マニラからの焔硝の買い付け量から行くと
120丁しか持たないことになるが、これも少なすぎる。
鉄砲の威力を速く知りながら、取り入れなかったのは、
大友宗麟の軍略化としての才能はあるが、
兵法家としての才能のなさだろうか?
はるか、南蛮に目を向けながら、
近代化できなかった宗麟の甘さであろうか?
大分に約4,000名の留学生を持ちながら、
財産を生かしきれない今の大分とリンクするかもしれない。
 佐伯運動グラウンド 佐伯球場
佐伯運動グラウンド 佐伯球場
韓国のプロ、アマの野球チームが、
今年から、佐伯、津久見、大分などでキャンプするようになったのも、
大分の元来持っている外国人を受け入れる力だろう
1550年ごろの府内はポルトガルの香り
象が歩いていたんですよ
博多港も大友宗麟が管理していました。
大阪の堺の街とほぼ同規模だったそうです。
大友宗麟が22歳の頃ザビエルも来ました。
沖の浜では、明船の積み下ろしも
行われていたんでしょうね。
1570年過ぎにはポルトガル船も着いてたみたいです。

貿易港跡記念碑 勢家町
最初は琉球王国との交易を望みましたが、
琉球王国は、ポルトガルが、マラッカを占有したのを
警戒し断わりました。

マラッカ王国
1511年ポルトガルはインド総督アマフォンソ・デ・アルブケルケは、
18隻の艦隊と800名のポルトガル人を率いてマラッカ征服
日本の金や銀が目的だったみたいです。
何しろ、黄金の国 ジパング ですものね。
日本の黄金伝説は、奥州平泉の金色堂が十三湊経由で
中国に伝わり、マルコポーロへと伝わっていったようですね。
1500年代は、本当に大航海時代だったのですね。
しかし、この時代は、征服という行為が当然のごとく
行われていて、悲しい歴史も世界中で起こっております。
府内にポルトガル船が着始めたのが1500年代中頃からで、
ちょうどこの頃です。
2012年のJR大分駅前の高架完成に合わせ、
南蛮の風が吹いてくる。
>
戦国大名の大友宗麟がおさめた中世の府内を
イメージし広場内の照明にはステンドグラスを使用し
>
雨や日差しを除く歩道の屋根は、チタンを塗った幕を
使用し、帆船のイメージしたデザインを整備の予定

15世紀中頃のポルトガル船
きっと、心地よい南蛮の風が吹くでしょう。
1月17日より、大分市の大道陸橋が全面通行止めとなり
8月11日に新しい姿が見れるでしょう。

長い間本当に御苦労さまでした。
また、新しくなって違う姿を見せてください。
大道陸橋北の歴史を書かせていただきます。
江戸時代において、大道峠への街道が分岐する
三叉路となっていた。
明治時代、外堀は、西新町通りと南新町通りとなり、
大分市、南西端の交通の要であった。
1945年 焼け野原となる。
1946年に工事が始まり、昭和30年代に終わる。
旧三叉路より200メートル離れた大道陸橋北交差点が
市街地中心へと移る。

大道陸橋北交差点1月14日撮影
国道57号線起点 国道442号線起点 国道217号線終点
国道210号線終点 国道197号線終点 国道10号線
と交差しており、大分市の要」となっている。
大分の人はシャイなのか?
それとも、用心深いのか!
外国人の方ともっと気楽に話しましょう。
大分は医療最先端の県です。
昨年、メディカルバレー構想なる会が立ち上がりました。
http://www.san-gaku-renkei.com/news_a95AQqK4Q.html
大分から宮崎にかけての構想です。
大分には、人工腎臓で最大手の会社があります。
佐伯と三重には血液回路と生理食塩水を作っている
会社があります。
1500年代には、大分には府内病院がありました。
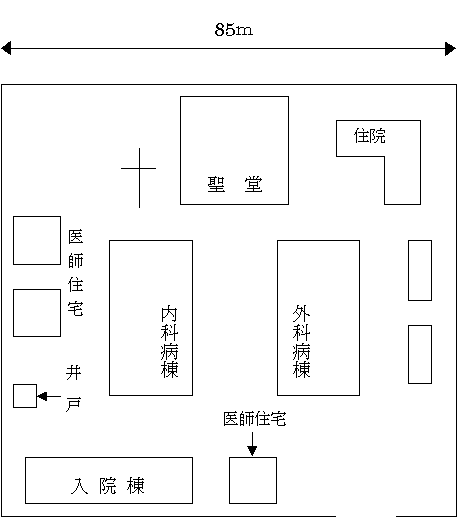 府内病院
府内病院有名な医師ルイス・アルメイダが1557年私財をなげうって、
内科、外科、ハンセン氏病科の病院と当時、間引きを救うため
乳児院を開いた。
 ルイス・アルメイダの像
ルイス・アルメイダの像すごいことです、この時代に外科手術も行っていたなんて。
現代でも、外国の方は、保険が使えず悩んでいる方や
どの病院にいけばよいのか、急病の時はどうすればいいかなど
悩んでいます。
外科と言えば近世になりますが解体新書で有名な中津の前野良沢がいます。
1771年杉田玄白とともに解体新書を書きましたが、
自分の名前は出さなかったみたいです。
 解体新書
解体新書昨年、中世大友府内町跡よりワイングラスでは
ないかという、ガラスの破片が見つかっている。
(大友氏遺跡発掘現場より出土)
南蛮貿易でもたらされた品物が、その当時使用されていたなんて!
府内の街に南蛮文化が花開いていた。
そのころから、カンボジア、ヨーロッパとの交易があった証拠でもある。
その頃の府内の人たちが、日本で一番国際的であったのかもしれない。

南蛮屏風
大分は外国の方を受け入れる土壌が1500年代から
出来上がっていました。
鉄砲が種子島に伝来したのが1542年ですが、
なんと、2年後の1544年にはポルトガル人より、
大友家に鉄砲が献上されていました。

最初に種子島恵時親子が2丁の鉄砲を
今の相場で1丁 5千万円で買ったそうです。
それが、1575年の長篠の戦いでは3千丁、
1600年の関ヶ原の戦いでは5万丁、
当時日本の有する鉄砲の数は世界の半数を所有していたそうです。
鉄砲と言えば、堺が有名です、大友でも作れたはずなのに
なぜ、造らなかったのか、
やはり、貿易に頼りすぎたのか?
鉄砲保有量も、マニラからの焔硝の買い付け量から行くと
120丁しか持たないことになるが、これも少なすぎる。
鉄砲の威力を速く知りながら、取り入れなかったのは、
大友宗麟の軍略化としての才能はあるが、
兵法家としての才能のなさだろうか?
はるか、南蛮に目を向けながら、
近代化できなかった宗麟の甘さであろうか?
大分に約4,000名の留学生を持ちながら、
財産を生かしきれない今の大分とリンクするかもしれない。
 佐伯運動グラウンド 佐伯球場
佐伯運動グラウンド 佐伯球場韓国のプロ、アマの野球チームが、
今年から、佐伯、津久見、大分などでキャンプするようになったのも、
大分の元来持っている外国人を受け入れる力だろう
1550年ごろの府内はポルトガルの香り
象が歩いていたんですよ
博多港も大友宗麟が管理していました。
大阪の堺の街とほぼ同規模だったそうです。
大友宗麟が22歳の頃ザビエルも来ました。
沖の浜では、明船の積み下ろしも
行われていたんでしょうね。
1570年過ぎにはポルトガル船も着いてたみたいです。

貿易港跡記念碑 勢家町
Posted by アイキュウ at 10:22│Comments(1)
この記事へのコメント
今でもわからない人が大勢いるが、文明と文化と理解し、把握できていたのではないでしょうか。
Posted by 通りすがり at 2011年04月30日 11:00




